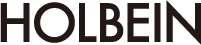佐竹 真紀子
SATAKE Makiko

風景のつづき
アクリル絵具、ジェッソ、木製パネル
27.3×27.3×2.0cm
2024年
Photo by 大江 玲司
ステイトメント
東北を拠点とし、海沿いの地域へたびたび通っています。訪れたまちで、土地の人びとと一緒に地域の地層の図を囲む機会がありました。人びとが暮らしてきたまちがかつて海であったこと。以前にも土地が津波をかぶっていたこと。その後も生活の跡が残っていること。地層は土地に流れる時間を淡々と記憶しています。
人一人ひとりの歩みも地層のように積み重なっているものだとしたら、大きな変化や出来事の訪れで、色変わりがそれぞれに起きていると想像します。 大きな変化が訪れる前にあった暮らし。変わり目を迎えた後も続くこまかな移ろいと、日々に宿る心情。それらの記憶をどのような形で携えていけるのだろうかと考え続けています。
土地を訪れて風景の中を歩く。出会った人から語りを聞く。何を見て聞いたのか、何が見えなくて聞けなかったのか、振り返るのには時間がかかります。ずっと何年も後になって、やっと触れたものに気づくのだろうとも思います。
触れた土地や人びとの記憶というのは、また、一片に近づこうとすればするほど、受け取った自分の記憶になっていきます。けれどもまずは備忘録として、できるだけ遅くて時間のかかる表現手法を用い、形に残すことにしています。
イメージした色彩で絵具を塗り重ねて、色の層をつくる。情景や語りを反芻しながら、層を彫りおこす。イメージと大きくかけ離れてしまったと思ったら再び塗りつぶす。また彫りかえす。近づけたと思ったらそこで手を止める。偶然性の高い手法でつくっていると、当初想像したイメージから離れながらも、巡り巡って、表現のはじまりにあったものへと近づけたと感じる瞬間があります。
近年では、制作した絵画とともに聞き書きのテキストもあわせて公開しながら、表現のはじまりにある土地や人のことを共有していく方法を探しています。

光という波
アクリル絵具、ジェッソ、木製パネル
80.5×117.0×3.2cm
2024年
画像提供:Cyg art gallery
奨学期間中の取り組みについて
活動においては、これまで通ってきた沿岸地域の近年の変化やきざしをまなざすとともに、はじめて訪れる地域を描く機会に恵まれました。東北に縁ある作家を企画展示するcyg art gallery(盛岡)での新作群の発表が、スカラシップ期間中の具体的な取り組みです。
制作の過程においては、土地を訪れて見聞きする行為が常に新鮮な行為であった一方、塗り重ねと彫り削りの手法を続けたが故の“慣れ”によるマンネリズムと形骸化が生じていました。
また、色の層をつくるにあたっては大量の絵具を使用するため、スカラシップ以前は、他社製品も含めより安価なアクリル絵具を選ぶことが多く、自己資金でホルベイン社の色材を試すことへの難しさを感じていました。そこで、スカラシップ期間中はアクリル絵具の色材(アクリル絵具マットタイプ)をあらためて揃え、絵具の層をつくるときに色彩の対比などの意識を高めました。
彫りの工程では、筆ややすりなど、彫刻刀以外の描画材を使った塗りとぼかしによる表現も多くなりました。画面上での模索自体が長くなったことも相まって、モチーフの軸でもある、見聞きした記憶に後から触れようとしたときに起こる不確かさや曖昧さへも一歩近づけたと思っています。ジェッソやアクリル絵具は、乾燥後に研磨するとより石のように硬質でひやりとした質感となるため、寒冷な地域の秋〜冬の情景を描くことに合っていると気づきを得たことも大きかったです。総じて、“描く”行為としてアクリルのスクラッチ技法を再考する機会でした。
こうした中で、モチーフとなる土地や使用画材の広がりから、色彩を用いること、美しい色彩で描こうとすることへの問いに改めて向き合いました。
震災や水害での被災を経験している土地へ足を赴き、災禍の出来事の過酷さではなく、その後の人びとの歩みにある逞しさ、覚えていたいと思う所作に美しさを感じ、描きたいと思っていること。何よりも、出会った人びとが、花や海や空を、それらの色彩を「今日きれいだね」と愛でながら暮らしていること。その所作を覚えておきたくて、絵具を用い、色彩で絵画にとどめたいという、表現のはじまりへ立ち返れたように思います。
社会で同時代的に起きている災禍や困難に心身が痛むときほど、自分が美しい色彩を選んで扱っていることについて、あるいは「美化」にまつわる問いについては、引き続き慎重に言葉を探していきたいです。

光という波(部分)
アクリル絵具、ジェッソ、木製パネル
80.5×117.0×3.2cm
2024年
画像提供:Cyg art gallery
奨学期間中に最も使用した
ホルベイン製品について
・アクリル絵具/アクリリック カラー[ヘビーボディ]
テクスチャーにマットな質感を求めており、これまでホルベイン製品ではジェッソとマットタイプの絵具のみ使用経験がありました。スカラシップの機会を得て、今回はじめてアクリリックカラー[ヘビーボディ]を使用しました。
アクリリックカラーは鏡のような光沢が特徴で、他のアクリル絵具と併用して色の層をつくるとその特徴が顕著に現れます。マットタイプの絵具でも、塗って乾燥した表面と彫刻刀での彫り跡では光沢の度合いが若干異なりますが(彫り跡の方が光沢が少なく、沈む)、アクリリックカラーを使用すると、塗ったままの高光沢な表面と彫り跡でより大きな違いが得られることになります。意図的に使用すれば表現の可能性が広がると感じました。
塗り重ねの過程においては、グラデーションをつくる際に鮮やかな発色が保たれました。彫る過程では、単色での絵具の固着力が高く、意図的に特定の色を剥離させることは難しかったですが、マットタイプに比べ支持体としている板材に色が染み込みやすい点、塗り重ねた前後の層への色移りが稀に生じる点で、予想外の色の彫り跡が得られました。また、絵具を乾燥させた後、水に濡らしヤスリをかけ、ぼかしを表現する際も、他のアクリル絵具に比べて水に溶けやすく、乾燥後のぼかし表現の幅も広がる可能性があり期待できます。
色のバリエーションがアクリル絵具 マットタイプより豊富な点も魅力的です。シャドーグリーンやペインズグレイなど、塗り重ねの色移りや研磨で分離色のような偶然も起こる複雑な色があり、マットタイプだけを使用していては出せなかった色味を得られました。
・アクリル絵具/アクリル絵具 マットタイプ
濡れ色と乾き色の変化が少なく、層の亀裂が生じにくく、ジェッソとの相性がよく、手法に対し最も使いやすいです。
・アクリル用刷毛/アクリリック ブラシ
普段の描画材としている彫刻刀は、一度の彫り跡の横幅が広くて1cm程度と、どうしても細かなタッチの連続になりがちです。今回、12cm幅の大きめのアクリリックブラシや、ぼかしに使いやすいリセーブルなどの筆製品を使用し、身体性のある大きなストロークを得ることができました。特にアクリリックブラシは厚塗りやグラデーションをつくりやすく、耐久力もあり、ヘラで塗り重ねた色の層とも違和感が出ず、使いやすいです。
プロフィール
佐竹 真紀子 SATAKE Makiko
個展
グループ展
受賞歴他
その他