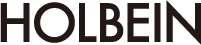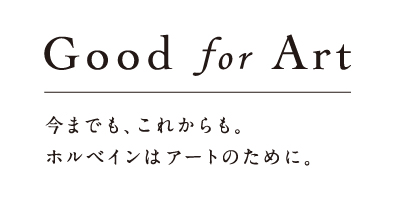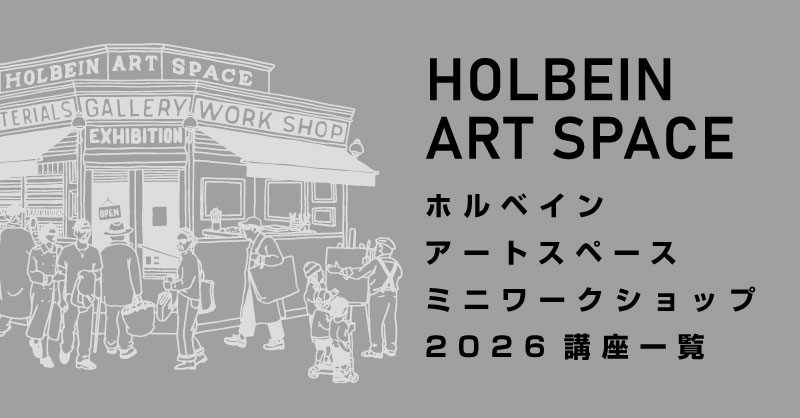アーティスト インタビュー vol.20「熊倉 涼子」

次代を担うアーティストの背景、作品に対する思い、メッセージを伺い、その素顔に迫る「アーティストインタビュー」。
今回は今後ますます活躍が期待される作家で、第34回ホルベイン・スカラシップ奨学生の熊倉涼子さんに、ご自身のアトリエで話をうかがいました。
今に至るまで
―いろいろな場所でお話ししているかとは思いますが、絵を描き始めたきかっけをお聞かせください。
子どもの頃に遡りますが、正直そこまで絵を描く子供ではありませんでした。
小学生くらいの時は漫画が好きで、その頃「お絵かき掲示板」という、ネット上で描いたものを投稿したり、その描いた絵に対してコメントしあったりしてコミュニケーションができる場所があって、そこで遊んでいました。
その時に、高校の美術科を受験するという子と知り合い、その子のブログかHPに投稿されているデッサンの絵を見て「すごい!」と、そんなことができるんだって衝撃を受けました。
鉛筆や絵具で、何か現実にあるものを紙の上に写しとる技術というものが、純粋に面白いなと思い、それで自分もやってみたりして、中学の美術の先生に予備校があることを教えてもらい、通うようになりました。
―高校に入ってすぐに予備校とは、美大を意識していたのですか?
行っていたのですが、「美大に行くぞ!」という感じではなく、本当に習い事の感覚で基礎科に通っていました。
通っているうちに、現役美大生の先生たちの美大生活や学外の展示会の様子を見て、すごくいいなと思って、私もこんなことしたいなと思ったのがきっかけですね。
―基礎科ですと、鉛筆デッサンだったり、粘土だったり、いろいろな画材と出会ったと思いますが、なぜ大学では油絵科を選ばれたのですか?
当時はあまり考えていなくて、いろいろやってみた中で、一番肌にあったという感じです。
あと油絵科って、最終的に油絵から映像や立体など、他の表現方法に移行する人もいるので、入ってからも他のことができるというのもありました。
けれど結局そのまま進んで今に至るという感じです(笑)
いろいろやってみたけれど、絵を描くのが一番得意だっただけなのかもしれないです。
―私は、人は最初から決意ができないもので、小さな決心をするというプロセスを少しずつ踏んでからできるものと思っているのですが、熊倉さんが油絵科に入って、この仕事を選ぶと決心した瞬間みたいなものはありましたか?
この時から決心したというタイミングがあったかというと、振り返ってみても全然なくて、大学を卒業してからも、描ける環境があるうちはやろうというスタンスでいました。
展示の機会があったら、なるべく参加するようにして、そうしているうちにいろいろな人と出会って、自分が思っている以上にいろいろな反応をくれて、そういう人達とコミュニケーションを取るうちに、もっとやっていきたいなという覚悟?みたいなものが、ちょっとずつ形成されてきたのかなと思います。

―現在の作品に至るまで試行錯誤されていたかと思いますが、最初はどのような作品を描かれていましたか?
学生の頃は、ぬいぐるみをモチーフに描いていました。
何をすればいいのかわからない時期があって、手近にあるものからやってみようという感じで始めました。
ぬいぐるみの外見というよりは、人がぬいぐるみを通して何かを言うということがあると思うのですが、物体でしかないものに人格を投影するということが面白いなと思って題材にしていました。
卒業した頃から、ぬいぐるみに衣装やお面をつけて、背景を置いて、劇の一場面みたいに構成をするようになっていきました。
その構成の参考にフランドル絵画の静物画を引用したりして、そういうことをしているうちに、モチーフを作って、組み立てて、絵画にするということが良いのではと思うようになりました。
それと同時に、モチーフがぬいぐるみだと、それに強くひっぱられてしまうことがあったので、描く対象を変えて同じ手法で描いてみようと思って、歴史上のイメージを引用して制作するようになりました。
―身近にあったぬいぐるみを最初に選ばれたのは、何か思い入れがあったからなのですか?
小学生の頃からあるぬいぐるみで、かなり自分の身近なものでしたが、大事だという気持ちを自覚しないままだなと思って描いていました。
―少し私の話になってしまうのですが、仕事で飛騨高山に行った時のことで、あそこには「さるぼぼ」という可愛いぬいぐるみのお土産があるんですね。
「さるぼぼ」とは元来、母親が娘の幸せを願って手作りで授けた習慣の中から出て来たらしいです。昔の、その地方の暮らしぶりは家族全員が野良仕事の労働力で、そこでは幼な子を育てている母親も容赦なくその一員でした。そうすると当然、子どもは一人残されて寂しいですよね?
さるぼぼは、それを紛らわす存在として機能していて、リアルな物は涎や手垢でガビガビになっていたりして、それが本物の“さるぼぼ”だという話ですね。
現在のお土産になっている存在とは全く異質な物が源流だと…本物はとても可愛いとは言えないと(笑)
今、お話を伺っていて、ぬいぐるみにはそれぞれそのようなストーリーがあるものなのかな?と思っています。
そうですね。
おそらく私は、ぬいぐるみにある個人的なストーリーには作品を作る上ではあまり興味がなく、それだったらとことん突き放した方がいいと思っていて、それが今の作品なのだと思います。
今アトリエにある絵は、展示場所がパン屋さんなので、パンの歴史やパンを焼く過程を絵に取り入れたのですが、自分発信で展示をするとなった時は、宇宙や天体をテーマにすることが多く、それはなるべく自分から遠いところからテーマを取りたいというものがあるからだと思います。

―今回の絵に古代エジプトから引用されているのも、ご自身から遠いところだったからなのですね。
因みにですが、特にどこの文明が好きなどはあるのでしょうか?
資料がたくさん残っているということもあると思いますが、古代エジプトが好きです。
展示とかよくやっていますが、何回行っても面白いです。
―実際、エジプトには行かれたことは?
ないですが、行きたいです!
―他の文明を引用されている絵はありますか?
今回はエジプトや西洋のものがほとんどですね。
パンに関する資料が残っているのが西洋に偏っていたので。
当時からパンは大事な主食で、小麦を育てて収穫して、粉にして捏ねて焼いてという沢山のプロセスがあり、社会の仕事のひとつだったようなので、壁画に残っていたりします。
―作品を描かれる前に、資料を集めたり、文献をよく読み込まれたりされているのですね。
そうですね。できる限り調べます。
―小麦は世界三大穀物のひとつですし、次は米とトウモロコシですね(笑)
米系は実は描いたことあります(笑)
―じゃ次はトウモロコシで!(笑)
トウモロコシも神話が結構たくさんあるので、描けそうです!
制作と過去の有名作家
―影響を受けた画家、もしくは作品がありましたら教えてください。
いろいろあるのですが、学生時代から何を描くにも西洋美術史上の絵画はいろいろ見ていました。
劇的でドラマチックなぬいぐるみの絵を描いていた時はロココとか、バロックとかすごく好きでした。
―17、18世紀あたりですね。
静物画を意識する時はフランドル絵画を見て、あとビザンチンあたりとかも好きです。
―おぉ!渋いところきますね!
ルネッサンスより前の時代は、なんというか…すごく素朴で、素朴だからこそ画家が無自覚にすごいことをやっていることが結構あると思っていて面白いです。
写本も、なんでこんなイラストを描いたんだろうと思うものもあって好きです。
あと、画家を挙げるとすれば、ピカソかセザンヌになると思います。
―ピカソとセザンヌですか!
絵画を描くということを客観的に見始めた時代にいた画家たちですね。
特に晩年のピカソの作品を見ると、古代から現代までのものを沢山見て知って、それらを奔放に扱っているところがあって、それがとても好きです。
―セザンヌの前のマネから「絵画とは何か」という問いかけが始まったので、仰る通り「画家が絵画を描くということを客観的に見始めた時代」ですね。
私は、セザンヌは絵でしかできないことを考えて描いた作家だと思っていて、熊倉さんの作品と通じる部分があるように感じます。
セザンヌは、これは狙っているのか天然なのかわからない、そういう面白い所が結構あって、とても良いと思っています。
―話を少し戻し、晩年のピカソは自身が見て知ったことを奔放に使われていると仰っていましたが、その所をもう少しお話しいただければなと思います。
ピカソっていろいろな画風で描いていますよね。
―言い方が悪いですけど、ちょっと狂っていますよね(笑)
どこまでヤバくできるかを追求しているんじゃないかと思いました。
箱根の彫刻の森美術館にあるピカソ館がすごく良くて、素描とか陶器とか沢山ありますが、あれは結構…狂気の塊だと思いました(笑)
有名な話ですけど、ピカソは本当にすごく絵が上手くて、しかも若い時から。
―15歳くらいで完成していますね。
そこからどんどん解体していく姿勢がすごいなって思います。
―本人が言っていましたが、4年くらい修行して描画力を会得したらしいですね。
4年かけてできたから、それが確実に自信になっていて、だから逆に自由になれたのだと思います。
宮本武蔵の守破離ではないけれど、型を知り、それを破って離れるみたいな、そういうものを体現している感じかもしれないですね。
憧れますよね。
憧れますね~。

ホルベイン・スカラシップ奨学期間
―ホルベイン・スカラシップ奨学期間を終えて2年ほど経ちますが、使用する画材や制作の流れ、考え方など、現在の活動に何か影響を感じられることはありますでしょうか?
スカラシップ奨学生の時にいろいろ絵具や筆を試せたので、絵の表情の引き出しが増えたように思います。
描く力でゴリ押しするところがあって、元々は質感へのこだわりとかあまりありませんでした。
ですけど、筆もいろいろ試したり、絵具も何種類か見てみたりして、幅ができたのかなと。
1枚の絵の中にいくつかの描き方を込めることが好きで、がっつり描写するところもあれば、ストロークで済ますところもあり、引き出しがあればあるほどいいと思っているので、それが細やかに増えたのは嬉しいです。
―本当に多彩ですよね。
非常にテクニカルなことを駆使されて、丹念に描かれているなと思います。
特に良かったと思う画材などありますか?
油絵具の「ヴェルネ」が一番好きですね。
―それは何故でしょう?
ヴェルネは作家にお話伺うと、高評価いただいていますが?
透明度と発色がとにかく素敵です。
―ありがとうございます。
ヴェルネは透明度が高くてとても良いのですが、高価なのが玉に瑕ですよね(笑)
そうですね(笑)
スカラシップ奨学期間の最後の画材提供の時、駆け込みみたいに沢山いただきました。
絵具の乗り具合も、少し説明しにくいのですが、触覚的に今まで触ってきた絵具と違っていて、作家の中でも話に出てきますし、画材に拘りのある作家さんも良いって言っていました。
―ヴェルネの土系(アンバー系)の色は、世界の中でも上位に入るほど透明度が高いです。
テールベルトは本当に他社と全然違いますね。
私はベーシックな色を主に使うので、そこが綺麗だと一層目から楽しくなります!
―熊倉さんの絵を見て、非常にグラデーションが豊富な絵だなと思いました。
グラデーションはどのスタイルの絵にも入っていて(もちろんグラデーションを使わない絵もありますが)、画家にとっての生命線のひとつだと思います。
熊倉さんはグラデーションに対してこだわりを持っていらっしゃるように感じましたが、どうでしょうか?
それこそ、筆に助けられた部分があると思います。
実は、かなりグラデーションは苦手だったのですが、スカラシップでいろいろ筆を試して、筆が合っていなかったからグラデーションが苦手だったことがわかりました。

制作活動を振り返り、その先
―少し難しい質問になるのですが、あなたにとって絵具は何でしょうか?
私は写実的なものを主に描いているので、何にでもなれる物質かなと思います。
不思議ですよね。顔料っていう粉と糊なだけなのに、空間が作れたりゴツゴツした質感が作れたり、面白い物質だなと思っています。
かなり素朴な答えになっちゃいましたが(笑)
―いえいえ、本質的なお答えでした。
画家にはいろいろな方がいますが、画家は絵具に何かを託していくものと、私はそう解釈をしています。
いろいろな選択肢がある中で美術というのは、かなりプリミティブ(原始的)なもので、だからこそある自由というものがとてもいいなと思います。
―制作過程について、今思えば過去にやっていて良かったこと、逆にやっておけばよかったことなどがありましたら教えてください。
他の人の展示をたくさん見ること。
あと、自分で企画を作ったり、それをアーカイブとして纏めていたりすることが、やっていて良かったなと思います。
―「展示をたくさん見る」というのは、同年代の作家の展示をでしょうか?
いえ、もう何でもです。
今は時間が取れなくて以前ほど展示に行けていないのですが、学生の頃は目に入った展示をすべて見に行っていた時がありました。
学生の頃は八王子の方にいたのですが、週に何回か都内に出て、自分の好き嫌い関係なく全部見ていくと、自分の尺度もなんとなくできてきたり、描き方の勉強になったり、逆に似たようなことをしてはダメだなと思ったり、そういうサンプルみたいなものが増えて、たくさん見ておいて良かったなと思いました。
―最近は特に見に行かない人が多いらしく、ある学校の先生も同じようなことを仰っていました。
SNSで見ているからなのかもしれません。
それはすごくわかります!
SNSで見て、見た気になっちゃいます。
スカラシップ奨学生に選ばれた時、同じくスカラシップ奨学生に選ばれた作家の作品をSNSでチェックしていたのですが、正直その時はわかりませんでした。
その後、スカラシップ成果展をした時に初めて実物を見て、こんなことしていたんだって気づいて、月並みですけど、やっぱり現地で見ることはとても大事だなと思いました。
作品単体だけじゃなく、どういう風に空間作りをしているのか、作品同士の関係をどうしているのかわかりますので、そういう時間を取るのは大事ですね。
―いろいろな作品を見てみて、今の日本の美術業界をどう感じますか?
多種多様だなと思いました。
私より少し上の世代は、絵画を描くことに意味があるのか問われる時期にいたと思うのですが、今は作家も多いし、デパートや企業も参戦してきたりして、発表する機会もすごく増えて、やりやすい時期になったように思います。
ひとくちに美術業界といってもいろいろな場所があるので、どの場所に自分を置くかを考えなければいけませんね。
見る側も、絵を描くという行為に疑問を抱く人も少なく、寛容になってきたと思いますが、私はただ好きにいい感じに描くだけでは意味がないと思っているので、描くことへの疑問を持ちながら制作しています。
―素晴らしいですね。ギャラリストもそういう方が増えていると思いますか?
そうですね。
元コレクターの人だったり、まったく関係ない業界だったり、いろいろなギャラリストがいるので、受け入れてもらえる余地は広がった、といった状況になったと思います。
―最後に、これからどのように活動を広げていく予定でしょうか。
新しく挑戦したいことがありましたらお聞かせください。
これまでは資料ベースで制作することが多く、本を読んで興味が湧いたことをテーマにし、資料を集めて進めていくことが多かったのですが、今は個人的なリアルな出会いから制作を始めていくことに興味があります。
昨年、古美術のギャラリーで展示をする機会があり、そこのコレクションをモチーフにして制作を始めたのですが、それがすごく新鮮でした。
前回、パン屋さんでやった二人展では、パン屋でやることと、もう一人の作家と一緒に展示するという条件からできた作品もあって、そういう始め方もいいなと思い始めました。最近、骨董市に行って、手に入る範囲ではありますが、少し古いものを買って見たりしています。
お店の人に「これは何ですか?」って聞くと、「わからないんだよね」って言われて、「なるほど」と言いながら買ったり(笑)
誰が作ったのかはわからないけど、100年、200年前の小さなものを集めて、そこから制作を始めてみたり、旅行先で出会ったものから始めてみたり、実際の出会いから始めるっていう制作もしてみたいなと思っています。
レジデンスとかにも興味ありますね。
―今、熊倉さんの素晴らしい作品に囲まれていますが、今後の展開も楽しみです。 本日はありがとうございました。

プロフィール
熊倉 涼子
KUMAKURA Ryoko
個展
グループ展
受賞歴他
HP https://www.kumakuraryoko.com/