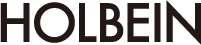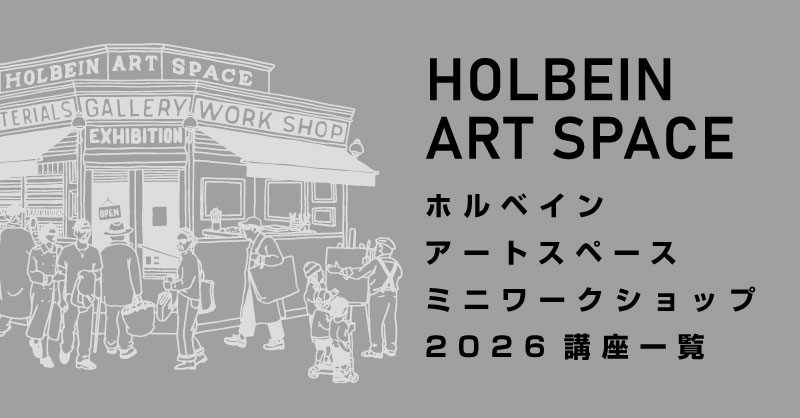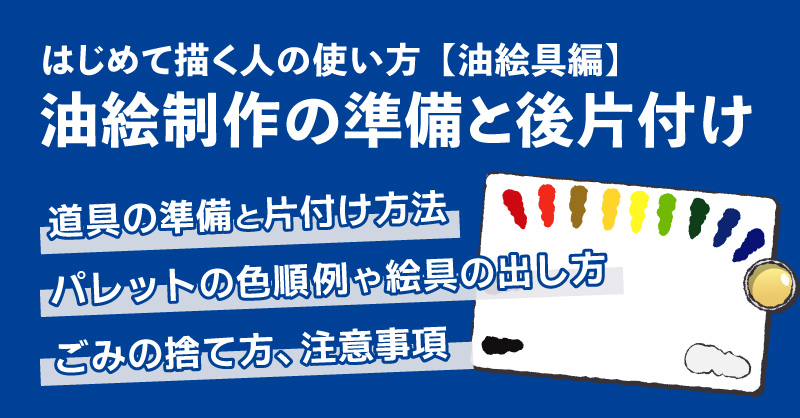色材の解剖学(25)日本画の顔料

色材の解剖学では、色材に関する基本知識から専門的な内容まで制作に役立つさまざまな情報をご紹介します。
日本画の顔料
深みをもった色調、ザラっとした画肌…。日本画には西洋画にはない独特の味わいがあります。今回は日本画に使われる岩絵具の顔料の「粒子の大きさ」と「材料の変遷」に着目して、日本画の特色と可能性について述べていきます。
粒子の大きさ
表を見てみましょう。まず気付くのは、岩絵具に使われている顔料は油絵具に使われている顔料と比べて粒子径が大きく、小さいものから大きいものまで幅広く使われていることです。
| 顔料種類 | 組成 | 平均粒径(㎛) | 吸油量 |
| ウルトラマリン顔料 | シリカ、アルミナ、ソーダ硫黄錯塩 | 4.1 | 41 |
| フタロシアニン顔料 | フタロシアニン | 0.03 | 64 |
| 天然岩群青8番 | アズライト | 65.6 | 22 |
| 天然岩群青12番 | アズライト | 19.7 | 25 |
| 新岩絵具(美群青8番) | ガラスフリット+コバルト | 65.0 | 24 |
| 新岩絵具(美群青12番) | ガラスフリット+コバルト | 21.3 | 27 |
| 合成岩絵具(優彩9番) | 水晶末+フタロシアニン | 34.5 | 40 |
| 合成岩絵具(優彩11番) | 水晶末+フタロシアニン | 26.2 | 44 |
岩絵具は水中での顔料粒子の沈殿速度を利用して分級されます。粉砕した鉱物を水中に沈めると、大きな粒子は重いため早く沈み、小さい粒子は軽いのでゆっくり沈みます。これを水簸分級(すいひぶんきゅう)といいます。
岩絵具のラベルには、3番(粒子径約170㎛)から10番(約10㎛)までの数値が表記されています。粒子径が最大のものが3番で、細かくなっていくに従い番号は大きくなっていきます。そして、大きな粒子は深い色、小さな粒子は明るい色になります。岩絵具をつくる職人たちは、群青や辰砂、緑青など、効果な鉱物顔料がもたらしてくれた色に、水簸分級という手段を用いて”深みの幅”を持たせたのです。
岩絵具にはこんな約束事があります。
(1)下塗りには粗い顔料を、上塗りには細かい顔料を使用する。
(2)下塗りには濃度の高いにかわ液を、上塗りには濃度の低いにかわ液を使用する。
(1)は絵肌作りの原則に基づいたもの。(2)は下が薄く上に濃いにかわ液がくると、上の収縮で画面に亀裂を生じるという、にかわの特性を考慮した技法です。この2つは”深みの幅”を活かすために生まれた岩絵具の技法です。
顔料の変遷
日本画は伝統的に天然岩絵具(鉱物を粉砕・水簸分級してつくった顔料)を使ってきました。これらの顔料には天然物特有の不純物が含まれているため、色調に独特の深みを持っているのが魅力です。焼成することにより、色調を変えることができるのも特長です。しかし、化学的に不安定なものが多いこと、焼成すると有毒ガスが発生するものがあること、材料が高価なで希少なこと、色数が少ないことなど、欠点もありました。これらの欠点を補うためにつくられたのが、昭和30年代に登場した新岩絵具と40年代になって開発された合成岩絵具です。以下はその組成と特徴です。
■新岩絵具 人工顔料を使った絵具。着色ガラスを粉砕してつくる。天然岩絵具同様、水簸分級が行われ幅広い粒子のものがあり色数も多い。にかわ液ともよくなじみ描画の際の違和感も少ない。品質は安定していて、焼成による色変えはできない。
■合成岩絵具 一般的に方解末に染料を染め付けた方法でつくる。天然岩絵具や新岩絵具にはない色、彩度の高い色が得られるが、にかわ液への染料の溶解、耐光性の低さが問題となる。
ホルベインでは「水晶末」に、耐光性のある顔料をコーティングした合成岩絵具を製造・販売していました。油絵具等と同じ顔料を使用しているため、鮮明な発色、大きな着色力、高い耐光性のある製品でした。水晶末表面に顔料粉末を定着させた構造の為、支持体にしっかり接着させるためにはにかわ液の濃度を上げることをおすすめします。

日本画絵具 優彩
※生産中止のため、在庫がなくなり次第終了いたします。
色材の解剖学は順次資料室へ収録していきます。