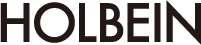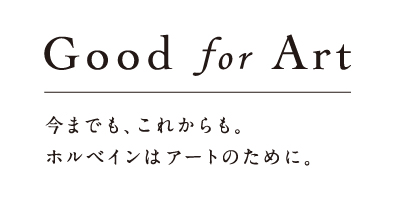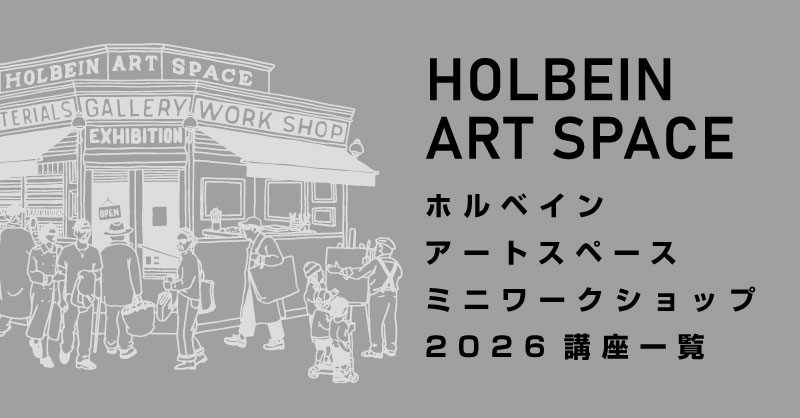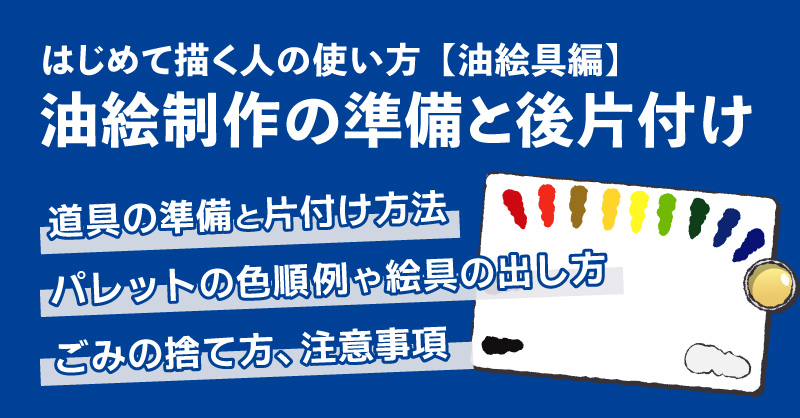アーティスト インタビュー vol.11「内藤 亜澄」

今回は今後ますます活躍が期待される作家で、第29回ホルベイン・スカラシップ奨学生の内藤亜澄さんに、ご自身のアトリエで話をうかがいました。
表現すること
―明るい色彩で描かれているが、どこか深み、重みのあるストーリー性を感じる内藤さんの作品は、そのファンタスティックな印象の中に内包された、内藤さんの独特の世界観が大きな魅力です。
この表現が生まれた背景とは、いったいどのようなものなのでしょうか。内藤さんに直接うかがってみると、そこにはたくさんの興味深いエピソードがありました。

―内藤さんが絵を描くようになったきっかけを教えてください。
昔から絵を描くことはお好きだったのですか?
そうですね、昔から描くことは好きで、小さいときは好きになったものはとりあえず描いていましたね。
「大きい」「強い」「速い」「カッコいい」みたいなのが大好きだったので。例えばクルマとか。動物も強いものが好きでした。シャチ、ライオンとか、恐竜とか。もう少し成長するにつれて、そういったものよりファンタジー小説が好きになって、その世界を描いてみたいと思うようになりました。 “ファイナルファンタジー”というゲームがありますが、そのデザインを手がけた天野喜孝さんの絵にすごく興味を持ちました。そこではじめて「このひとの絵の描き方って、何か不思議だな」、と思いましたね。
再現的なものではなくて、「そのひとなりの表現」というものを意識するようになったのは天野喜孝さんの作品を観たからで、“ファイナルファンタジー”や“ロマンシング サ・ガ”などのゲームがありましたが、そのキャラクターデザインなどにすごく惹かれました。 そこから次第に「再現的」なものよりも「表現」みたいなものをちょっと意識するようになったのは、多分“ファイナルファンタジー”の影響だと思います。
―今も何かしらその影響はありますか?
一時期、やっぱりそうしたファンタジーみたいなものからちょっと距離を置きたくなる時があって、20代の時とかはそう思ったときもあるのですが、逆に今は当時の影響を感じますね。
また、自分に子どもが生まれて、子どものみているもの、好きなもの、好きになるものをみていると、当時の自分がみてきたものがやっぱり今の自分にすごく影響があるということも感じます。
―小さな頃はやっぱり学校で使っていた絵具やクレヨンを使って描いていましたか?
私の父が設計の仕事をしていて、家に紙がたくさんありました。設計図の裏を使ってよく描いていました。鉛筆、ペンが好きでしたね。
―それでは中学に入ってから美術部に入られたのですか?
いえ、中学の時はサッカー部をやっていまして(笑)。
スポーツの影響も結構大きかったりしますね。時間と目的意識を持って、ここからここまでをしっかりやる、とか。
「きっちりやる」、というのもスポーツの影響かな。その辺、前向きです(笑)。文化系というと、スポーツじゃなかったりするとは思うのですが。
―では学生の頃は寧ろサッカーなどのスポーツに力を入れていたのですか?
中学の時は、もちろん本を読んだり映画を観たりすることも好きだったのですが、ずっとスポーツをやっていましたね。
中学の運動会ではみんなで気合を入れて組体操をやりました。リーダーみたいな友だちがいて、彼がみんなをまとめ上げて円陣を組んだりして、その時はすごく楽しかったのですが、その後、先生がその時のヴィデオをみせてくれたときに自分の様子をみて、「これが自分なのか」と思いました。なにか他人のようで「すごく無理をしているな」、と思ったのですね。
それからは共同で何かをやったり、それに対して感想をいったりすることは自分にはあまり向かないな、と思いましたね。
―そのことを、客観的に自分をみることによって気付かれたのですね
その時に「ちょっと違うな」、と思ったのははっきり覚えていますね。
高校でも(サッカーを)続けてみたのですが、やっぱり続かなくて1年の時にすぐに辞めてしまって、そこからもう音楽や映画とか、そういう方面に興味が出てきてしまって。
それからは友達と学校の帰りにレコード屋に行ったりとか、そういう感じでした。
―そこでも絵画表現に行かなかったのですか?
そこはなかなか結び付かなかったですね。でもなにかこう、表現したいという気持ちがあったのですがそれが何なのか、その時はよくわからなかったと思うんですよね。
高校でも周りの友だちは文化祭や体育祭にすごく力を入れていましたが、ぼくもなにかの方法で自分をアピールしたいのだけど、それがなんだかわからない、という高校時代だったような気がします。
―自分も表現したいけれども、何をどうやって表現したらよいのかわからないという感じだったのですね。
ですから、いろいろな表現者に対して憧れはありましたね。ミュージシャン、映画監督とか…。

絵を描くこと
―そこから絵画表現に行きついたというのは、何かきっかけとかがあったのでしょうか?
いろいろなものに興味を持ちつつも結局、自分のいちばんの根底に絵が好き、ということがあったのだと思います。
なので、進路を決定するときもやっぱり最終的には美術方面にしようかな、と思いましたね。
―小さな頃に鉛筆やペンで描いていた絵の楽しさがベースにあったのでしょうか
自分がいちばんできるのがこれかな、と思いましたね。
―思ってすぐできてしまうというのはすごいですね。絵を描いてみたらやっぱり難しいと思う方のほうが圧倒的に多いと思うのですが
いや、それはもちろんこの後に痛いほど感じることになるのですけど(笑)。
―最初から油絵具を使われていたのですか?
学生時代はずっと版画をやっていました。銅版画でした。
集中して描きたいは描きたいのですが、絵具は当然、液体ですし、長い筆を使って描いたりするじゃないですか。
そうすると自分と支持体との間に距離を感じてしまって。もっとこう、体に抵抗が撥ね返ってくるような、つくっている実感が欲しくて、いろいろやってみたのですが、あまりしっくりこなくて。
その時に版画に出会ったのです。江戸川乱歩の小説の表紙のために「多賀新」という方が作品を作っていて、それに影響を受けました。
また、大学に山野辺義雄先生という方がいらして、版画協会の方でもあったのですが、先生の作品にもすごく影響を受けています。今も自宅の玄関に先生の作品が飾ってあります。
その先生に師事したのですが、既に高齢で引退間近だったので、ぼくが最後の卒業生なのですが、先生のアトリエに行って作品を見せていただいたり、そこで版画をずっと勉強させていただきました。
大学を卒業した後も2年間ほど版画をやっていました。2008年か2009年くらいだったと思いますが、版画協会に作品を出品した最初の年に入選しました。
しかし次に出品した時に落選して、上野まで作品を取りに行きました。
その時にたまたま「VOCA展」がやっていて、それを観ました。自分と大して世代も違わない作家たちですが、作品のスケールが全然違う訳ですね。
技術的なことももちろんですけれど、コンセプト、中のスケール感が全然違って、圧倒されてしまいました。
版画の世界は、それはそれでもちろん素晴らしいのですが、版画という小さな世界だと技法的なことに集中してしまいます。そこでもっと技法的なことではない、作品のコンセプトや内面的なものに興味が湧いてきて、自分もスケールが大きい作品を作りたいと思うようになりました。
そこからですね。
―確かに銅版画ですとその特性上、表現方法にはある程度の制約がありますよね
はい。技法に集中しすぎて自分の内側の世界に入ってしまう感じがあって、ちょっと距離をおいた方がいいかなと思いました。
―それがきっかけになって油絵具を使うようになったのですね
そうですね。油絵具をはじめたら偶然、いくつか賞をとることができましたし、表現の自由さも感じました。
自分は集中して描くのも好きなのですが、大きい作品を描きたかったのだ、とあらためて気づきました。
しかし、それまで版画しかやってこなかったので、何をどうしたらいいかわからなくて。
―そのあたりはどのような感じで克服したのですか?
ドイツに“パウル・ヴンダーリッヒ”という版画家がいたのですが、彼は油絵具やアクリル絵具でも作品を描いているんですね。また、エアブラシも使っているんですよ。
なので、ぼくも使ってみようかな、と。
最初の頃はヴンダーリッヒをかなり参考にして作品をつくっていました。
―では絵画表現に関してはほとんど独学になりますか
はい、そうですね(笑)。
―すごいですね!あらためてびっくりしました!
その後に当社の「ホルベイン・スカラシップ」に応募いただきましたが、当制度のことは以前からご存じだったのですか?
僕は美術大学出身でないことにすごくコンプレックスがあって、他人の経歴を気にしてしまうところがあります。
ほかの方の経歴をみていると、受賞歴の中に「スカラシップ認定」というのがあって、「スカラシップ」って何だろうと思い調べてみたら、こういう制度があることを知って応募してみようと思いました。
―認定前もホルベインの絵具は使用されていましたか?
使っていました。やっぱり最初に手が出しやすいというか。ホルベインやクサカベがいちばんとっつきやすいところだったので。
でも描き味は全然違いますね。ホルベインは適度な粘り気みたいなものがあって、ぼかしとかすごくやりやすいです。
自由と制約、進化と束縛
―ありがとうございます
話は変わりますが、今回のインタビューが決定した後、いろいろと内藤さんの作品を観てみたのですが、2016年頃から現在の作風に近くなった印象があります
自然に移り変わっていった、という表現がいいのかな、と思います。
当時は「内側と外側」というコンセプトで作品をつくっていたと思うのですが、当時描いていた内側というのはより記憶とか、自己の記憶や他者の記憶とか内面的なものと実体とのズレみたいなものを描いていたのですが、当時扱っていた内側だと内容がプライベートすぎて、あまり客観性が保てない極私的なものでした。
当時から子どもなどモチーフに描いてはいるのですが、描き方というか、コンセプトが結構変わってきていて、同じ子どもを描いているのですが基となるものが全然違って。
素材に関して少し泡沫な話になってしまうのですが、子どもを描きだしたきっかけみたいなものがありまして、アーサー・C・クラークのSF小説で「幼年期の終わり」という作品があるのですが、それがすごく衝撃的なラストで、子どもが大きな意識体に取り込まれて世界が滅亡する、という話なんです。
「おとな」ではなくて「子ども」なんですよね。子どもとおとなの間で隔絶された何かがある。その時、自分が思い描いていたラストシーンがエドワード・マイブリッジの記録写真とすごく一致するところがあったのです。
それから、なぜ子どもとおとなで分けられたのか、なぜエドワード・マイブリッジの写真にこんなに惹かれるのか、自分でいろいろ考えていたのですが、その写真は子どもが恐らくおとなに指示されて、歩かされていたりとか、こうした動きをしてくださいとか、記録写真みたいなものが撮られているのですが、動きの美しさと同時に、なんだかちょっと恐ろしさみたいなものを感じました。「規則の中にある恐ろしさ」というんですかね。なにか神々しさもあるんですけど、同時に未成熟さとか、不明瞭さ、不確定さみたいな要素がいろいろ内在されていて、それが表現されている。そこにすごく惹かれましたね。その姿に惹かれて子どもを描きはじめたのです。
自分にも子どもができて、ある時、友人の子どもと一緒に遊ばせていた際に、子どもたちは床の板の目をつかってジャンプして遊んでいました。子どもたちは初対面同士だったのですが、どうやらなにかルールがあるらしい。こうしよう、とか一切約束などはしていないのですが自然にルールができていて、どうやら成功、失敗があって。それだけだと、物体の見た目ではなく、機能的な部分を取り込んで遊びをつくりあげるという、ゴンブリッヂの「棒馬考」を見ているようでした。
しかし、そこに言語的取り決めはなく、自然にルールみたいなものが醸成されていって、最終的にどうなるかというと、そのルールに自ら縛られてゲームがやりにくくなっていくんですね。その時に「進化」とか「発達」とか、そういうものを意識したというか。子どもって自由なもの、という印象があると思うのですが、果たして本当にそうなのか?自由といっても何からの自由なのだろう、と。
もしかしたら子どもは自ら縛られに行っていないか?ということを感じたのです。おとなからすると、子どもたちは自由でいい、でも子どもはもしかしたらそういう法則、規則などを自ら求めているのではないかな、と感じました。
その不確定さ、不安定さ、社会的な規範の無さみたいなものを顕したくて。アクリリック[フルイド]や[インク]を使って流動的に、たらせば自然に流れていきますよね。その流れを利用して、そこから形を見つけて、その形からヒントを得て描いたりということもやったりしてみたのですが、やはりそこにも当然、法則があるんですよ。色にも広がりやすい色、広がりにくい色、交じりやすい色とか、いろいろ法則があって。
やっぱりいたるところに法則があるんですね。あらゆるものが決められた法則に従って進化していく、その恐ろしさみたいなものを感じて、それを「子ども」というところで表現しようと思ったのです。
常に「法則」が後ろ側にあるということを。
―進化するにはルールに従わないといけないところもあると思うのですが、しかし最終的にはそのルールに束縛されて行き詰ってしまう、そんな恐怖を表現したいということなのでしょうか
社会的に制度を決めることもあると思うのですが、もう少し人間の本質としての規範、規則とか、意識とかいうものが先にあって、人間が大きくなるにつれて、差別とか争いとかをする方が自然で、本来そういうものだと思うんですよね。そういう自然の法則みたいなものがやっぱり恐ろしいところなのだ、という恐怖を描きたいと思っています。
つまり、無邪気に遊ぶ先に、争いや差別が生まれる構造を持っている。
作品ではけっこう明るい色を使って表現したりしているのですが、その後ろにある恐怖を描いています。
―確かに内藤さんの作品は色つかいがきれいで、単純にそこに惹かれることもあると思うのですが、鑑賞しているうちにふと背筋が寒くなる感覚を憶える瞬間があるのです
その感覚が不思議だったのですが、今のお話で腑に落ちた感じです
アリストテレスには“エイドス”と“ヒュレー”という考え方があります。
“エイドス”とは本質的なものがすべて詰まった種子、種の在り方で、種ってそれだけ見てもわからないですが、必ず自らのDNAの設計図に従って成長していき、それがリンゴになったりとかする訳です。そこでやっぱり人間も子どもの状態からそういう設計図みたいなものを持っているのだろうな、と思うのです。自然の法則、育ちの恐怖みたいなものを常に感じますね。
なので、本質的に「自由」というものは、もしかしたらないのかも知れませんね。
ホイジンガの作品で“ホモルーデンス”という、遊びがあって人間が進化していく、という論説があります。
文化よりも先に遊びがある、でもその遊びの定義として、自由な事と共同体意識、共同体の規則みたいなものがなければ遊びとは認定できない。完全に自由だと遊びにならないですからね。ですから進化のきっかけが遊びだとするならば、やはり規則が必要で、規則の中でこそ進化を遂げていく、新しいものに生まれ変わっていくだろう、ということに私はいちばん興味を持っています。
―先ほどのお子さんのお話もそうですよね。遊んでいるうちに自分たちの中で暗黙のうちにルールが決まっていく
そして、自ら縛られていく(笑)。
逸脱するにしても逸脱の作法みたいなものがあるんですね。
僕、学生時代にパンクロックが好きだったんです。パンクというと、社会から外れるような感じがしますが、それも作法なんです。外れ方にも作法がある。反社会的なものもみんな同じような外れ方ですよね。そこにも型が、外れ方にも型があるのですね。
ジャズも即興でいろいろ演奏しているように見えても決まりごと、スケールに従って演奏している訳ですし。完全に決まりごとがあってどこに行ったってそこから逃れることはできないんですよね。そうしたところがいちばん興味あるところですね。

内藤さんとホルベイン
―いまはアクリリック カラー[フルイド]など、アクリル絵具も使用されているのですね。
はい、そうですね。最初、[インク]の滴りとか流れなどを使っていたのですが、油絵具との併用で親和性を感じられなかった感じがして、ホルベインへ質問したことがあります。
その際「恐らく内藤さんが今やっている技法だとこちらの方がいいのでは?」ということで[フルイド]をお勧めしていただいて、そこから使うようになりました。
実はホルベインのカスタマーサービスには何回か相談したことがあります(笑)。

―それは知りませんでした(笑)。
では油絵具はあまり使わなくなりましたか?
いや、やっぱり最終的には油絵具で仕上げています。
はじめの方に[インク]や[フルイド]をつかって流動的な動きをつくって、その上に油絵具で再び同じように描いてみたり。。
油絵具であの(流動的な)流れを表現することはできないので、[フルイド]の流れを参考にしています。。
そのまま[フルイド]がどういう動きをするのかをみて、その上に絵具を重ねることもありますし、動いた通りに油絵具で対応したこともあります。。
[フルイド]は独特な流れをつくるので。独特なマーブルはきれいですよね。
―ある素材の特徴を他の素材で表現するという、ひとつのアイディアということですかね。
素材の特性と子どもの身体性をあわせて描いていきたいですね。 スプレーなどけっこういろいろな素材を試したりしています。
―ホルベイン・スカラシップ奨学生だった時はいろいろな素材を要求し、お使いになられましたか?
そうですね、せっかくなのでいろいろ。普段使わない色とか試してみたり。
―それは内藤さんの表現になにか影響はありましたか?
やっぱり表現活動をしていく中では資金と時間、場所のことは大きいのです。そこで(スカラシップの恩恵で)資金のことを気にしなくなるので、せっかくだからいろいろな実験をしてみよう、という気になりますね。
制作にはいろいろと資金をかけたいのですが失敗が怖いのであまり思い切ってできないのですが、スカラシップという制度があると「チャレンジしてみよう」という気持ちになりますから、いろいろと実験させてもらいました(笑)。
―第33回スカラシップでは成果展を開催させていただいておりまして、支給前と支給後で作風などにどのような違いが出てくるのか、そこで発見することも多く、我々もすごく興味があります。
ところで、ホルベイン製品の中で内藤さんが特に気に入っているものは何でしょうか
いちばん使うのは油絵具なのですが、やっぱり[フルイド]は自分が実験した絵具の中でも色のきれいさと混じり方は独特のものがあって、すごく好きです。[インク]の光沢も気に入っています。
[フルイド]はぼってりとするのですが、[インク]だと、さーっと流れてくれます。その滴り、流れというのはすごく好きなので、その感じを出したい時は[インク]を使います。油絵具だとそれは難しいですね。
それと先日いろいろと相談させてもらったのですが、メディウムも独特の光沢があって気に入っています。 溶き油のちょっとグレードの高いものとかの光沢もすごくきれいですね。
急ぎの時はクイックドライングもよく使っています(笑)。これは使っている方が多いのではないですか?(笑)
―お付き合いも長いと思いますが、内藤さんにとってホルベイン製品とはどのような存在なのでしょうか?
ホルベイン製品って、絵をはじめようと思った初心者の時からプロになった今まで、ずっと使えますよね。
とっつきやすいと思うんですよ、ホルベインの製品は。でも、絵をはじめようと思ったときでもちょっと本格的にやっているような感じを演出できたり(笑)。
実際にプロになって使っていてもやっぱり信頼がおけます。
ずっと使える、長く付き合える製品だと思います。
―絵画のことにとどまらず、読書や音楽のこと、果てはアニメの話題まで、あらゆるジャンルに興味を持ち、しかも驚くほど博識な内藤さん。
インタビュー終了後も楽しい会話は尽きませんでした。
この尽きない知的好奇心が内藤さんの作品制作を支えているのかもしれません。
私たちは製品を通じて内藤さんをはじめ、アーティストをサポートしていきます。
プロフィール
内藤 亜澄
NAITO Azumi
個展
グループ展
受賞歴他
Instagram https://www.instagram.com/azumi_naito_/
Facebook https://www.facebook.com/azumi.naito.5