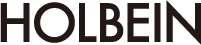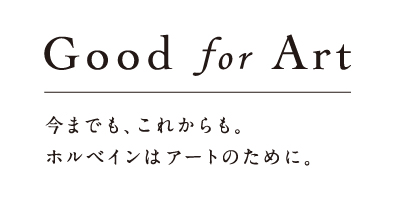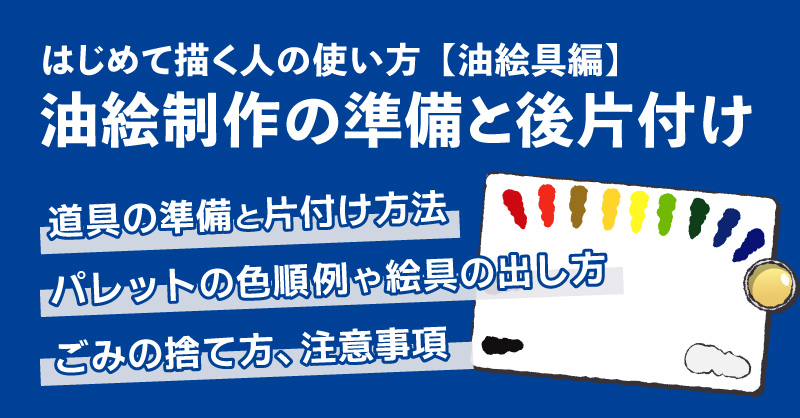アーティスト インタビュー vol.12「長嶺 高文」

次代を担うアーティストの背景、作品に対する思い、メッセージを伺い、その素顔に迫る「アーティストインタビュー」。
今回からは、最新の認定者である第35回ホルベイン・スカラシップ奨学生のインタビューをお届けします。
その第1回目は、今後ますます活躍が期待される作家の長嶺高文さんに、ご自身のアトリエで話をうかがいました。
Birth of the painter
―長嶺さんが作品を作り始めたのはいつ頃からか、教えてください
恐らく18歳ぐらいからだと思います。
もともと絵は好きでしたが、別にクラスに一人はいる「絵が得意なヤツ」って感じで。
大学受験の為の進路選択の際も「美大っていうものがあるらしい」、というぐらいの認識で、絵を描く事に興味はあったものの、結局その時は美大ではない大学に進学しました。
その時は学校の先生になるつもりで、教員免許をとる目的で大学に進学するんです。けれど、高校時代からそうなのですが、大学に入っても友だちが全然出来なかったんですよね。入学して、次第に勉強も熱心ではなくなって、とにかくボンヤリとした大学生活を過ごし始めていました。
それでインターネットばかりやっていたのですが、特に当時「お絵かき掲示板」というサイトにハマっていて。昔からずっと閲覧していたサイトなのですが、人と会話出来ない日々が続いて、毎日何かをしたという充実感がなくて、その喋っていない分や何やかんやを補うみたいな事だったのか、何となくそのサイトの中で絵を描き始めた、というのがきっかけになりました。
―そのサイトには、「絵を投稿する」という感じですか
そうですね。「2ちゃんねる」みたいに左側にジャンル(板)を選べるバーがあって、例えば版権板とかオリジナル板とかがあったと思うのですが、そこから板を選んで、スレッドを投稿するみたいな感じで、ブラウザの中のツールを使って絵を描いて投稿できるというサイトなんです。僕は今34歳なのですが、恐らく同世代ぐらいの人達の間では知名度のあるサイトだったと思います。
―最初はどういった画材を使われていたのですか?
画材というかペンタブを使ってました。
―そうですね、ペンタブですよね
アナログで描いた作品をスキャンするということではなくて
アナログは当時全く使っていませんでした。デジタル画材オンリーで。相当楽しくて、それこそ毎日の様に朝まで描いているぐらいでした。
そんな大学生活が4年生まで続いたのですが、依然として、誰とも関わらずに足早に帰宅する日々を過ごしており、そんな状態のまま、中学校へ3週間ほど教育実習に行くことになったのですね。そしてまあ当然というか。自分なりに頑張ってやっていたつもりではあったのですが、3週間面倒を見て下さった担当の先生から、最後に総評でハッキリと「あなたはまだ人として未熟なので、教育者にはならないでください」と言われて、自分でも「まあそうだよな」、と思ったんですよね。相当まずかったんだと思いますが。
それがきっかけとなった、という訳でもないですが、このまま世に放たれたらまずいな、と思ったんです。それでたぶん、逃げる事を徐々に決意していったのだと思います。
それまで絵画といえばゴッホとピカソぐらいしか知らなくて、美術館に行った経験もなかったのですが、どういった経緯なのか忘れましたが、佐伯祐三という作家を知ったんですよね。(eastern youthというバンドのアルバムのジャケットで知ったのかも知れません。)その教育実習に行く、少し前の事なんですが。
実物を見るのはそこからまた少し後になるのですが、当時あのパリのポスターの絵だったりをインターネットで見て、「これが油絵ってやつか」と思ったんですよ。油絵具を画面に塗りつけた痕跡がそのままに残されていて、なんというんでしょうね、イメージが描かれているのか、モノが、行為があるのか。なんかしら当時の自分に響くものもあったんだと思います。
デジタルと油彩なので当然かもしれませんが、自分がその頃描いていた絵と決定的に違っていて、この画材に触ってみたいと思ったんですよね。
いろいろ、何がきっかけと一言で言えないんですけど、なんというかそういう経緯があったりしながら。とにかくあの時自分がずっと座っている場所があって、そこから逃げたかったんですよね、多分。もうちょっと時間が欲しいというか。何というか、そんな感じで。22歳になって、みんなが就職活動に勤しむ中、美術大学への受験を始める事にしてしまったんですね。
―その以前は一般の大学に行かれていたとお聞きしましたが、そちらと比較して美術大学は長嶺さんにとってどんなところだったのでしょう?
そうですね、一番違うのは美大では友だちができた、という事が自分にとっては凄く大きな違いですが。
一般大学の頃は人と関りを持てなかったので、こういう場所だ、ということをあまり言えないのですが、美大だと、喋ったりする前にどんな作品を作っているのかを知っていたりしますよね。そうじゃない大学だと、隣の席で授業を受けているやつのことは話しかけてみないと中々どんな人かわからないじゃないですか。たぶんそういう事からくる差は凄くあるんじゃないかなと思います。
それと美大に入ったときは結構、僕は年齢がいっていたというのもあって、多少は気持ちに余裕があったのかもしれません。
違いをあげればいろいろあるのでしょうけど。
―アナログで描くようになってからが本格的な作品作りのはじまりになりますか?
デジタルで制作していた事が、現在の制作にも地続きになっている事がいろいろあるような気がしているので、どこからが本格的な、と言えるかのは少し難しい気がします。
それに、アナログで描き始めてからが本当に大変でした。
デジタルはつまり、光を使ってモニターの中に描く事が出来る、という印象があるのですが、現実の絵具というのはチューブから出すと立体物ですよね。それを塗りたくる、という事との折り合いがうまくいきませんでした。
結局4浪もしてしまうのですが。その原因の一つにはそれもあったのかなと思っています。
本格的にはじめようと思って新宿の美術予備校に入ったのですが、その「本格的にはじめよう」という気持ちは確かにそこからはじまっているとは思うのですが、本格的に描き始める事が出来始めるのは、そこから時間がとても経ってからの事だと思います。
モニターの向こうの空間にダイレクトにアプローチできるデジタル画材と、こちらの理、重量を受けたものを使いながら描いていく、ということのギャップが大変でした。
―予備校ではかなり制作に励まれた感じでしょうか
励みましたが、相当挫けさせられる事にもなりました(笑)。
油絵具を扱うというのは本当に難しくて「これは無理だな」、と思うぐらい。結局予備校にいた間では油絵具を使いこなすという次元に持っていく事はとても出来ませんでした。
22歳からの受験生だったので、ずっと予備校に通っている訳にもいかなくて、ほとんどフリーターとして過ごしている期間もその間、長くて。受験期の1、2月は予備校に行って、落ちたらまた3月から12月までコンビニで働いているという感じだったり。1年間丸々予備校に通っている年もありましたけれど。
一生懸命やっていましたけど、ネットの中でやっていた時に「出来るだろう」と思っていたことが全然実現できなくて、なかなか厳しかったです。
―いろいろな意味でジレンマもありましたか?
ありましたね。絵は上手くいかないし、藝大にはずっと落ち続けるし、同世代は就職して働いていて、「俺はいったい何をしているんだ?」と思っていました。3.11(東日本大震災)もその頃ですね。世の中も自分もめちゃくちゃになってしまったと思っていました。
―では予備校で勉強されていた時、絵を描くことが楽しいと思ったことはあまりなかった?
いや、それでも絵は楽しかったんだと思います。熱中していたと思います。予備校でもずっと人と喋る事は殆どなかったんですけど、何年も予備校にお世話になり、幸か不幸か、少しずつ喋れる人も現れました。絵を先生が講評してくれるっていうのも嬉しかったです。
けれど、多浪になっていき、受験絵画の事ばかり考える様になってしまい、それを反省して、作家としての自分の制作を模索する事を考え始めました。その頃には上手くいかない原因を自分なりにも考えて、鉛筆と紙から始めたり、とにかくドローイングをしたり、模索していました。
それが功を奏したのか、自分がやりたがっている事というのが、今考えると本当にぼんやりとしたモノですが、何となくこういうことなのかもしれない、という手応えを感じる様になり、それと並走する様に、人としゃべれるようになりはじめる、というか。
絵を通して吐き出していく事と、人との関係を築くという事が自分の中で噛み合っていくというか。
―では、絵を描くことが長嶺さんの支えになった部分があったということでしょうか
そうですね、すごくあったと思っています。
その後美大に入って学んでいく中で、自分の気持ちで描いていく、みたいなことって、あまり言えなくなってくるというか。作品が手元を離れる様な事が必要にもなってくるとも思う様になります。
でも、あの頃の自分が、なんというか、立ち上がろうとした時、もしかしたら今だってそうなのかもしれないですが、絵を描く、言語にならないことでもなにか形にする、形にならなくても出していたこと、吐き出していたこと、それらが多分、自己治癒となっていたのは間違いない、と思っています。
―今の作風になるまではいろいろな変遷はありましたか
あります。説明するのが難しくて、自分でもいろいろ整理がついていないところもたくさんあり、長くなってしまいそうですが。
模索して制作していく中でキーワードになるようなモチーフが立ち上がり始めていました。
その時は「窓」というモチーフが立ち上がっていて。当初は室内だとか家や家庭が気になっていたのですが、だんだん「窓」ばかりがフォーカスされてきて。
例えば、玄関と窓ってすごく違いがあると思うんですよ。玄関って開ければ入れる場所で、閉じれば拒絶するもので。それに比べると窓はまあ通常は入ることはできないものですが、外から中の様子はうかがう事ができる、というか。
通りに家があったとして、その家の室内と通りの間に、窓を隔てて、といいますか。開口部というか。この距離感が気になったのだと思います。
当時はその窓の中にある生活の光に何かしらの「存在」を見出していて、それに近づきたいのか、なんなのか、既知な世界の中に空いたブランクな場所。そういったものに対しての、この窓を通した距離感が、当時の自分にとってリアリティのあるものでした。
しかし次第にそれを「定点観測的」といいますか、自分が外側から観察している関係について疑問を抱く様になり、もっと関係に降りていくことを考えていかなければいけない、って思いはじめました。
例えば、身体は新陳代謝をして、数ヶ月も経てば本来なら別人と言っていいほどに細胞は入れ替わりますけど、脳や神経は新陳代謝をしないらしいんです。ですがたぶん、脳みそは細胞とは何か別のものが代わりに代謝しているのかもしれない、と想像するんですね。記憶というものが仮に一つの形を持ち、それが脳みそだとするならば、それは経験という外界から形成され続ける流体かもしれなくて、つまり自分と呼んでいるものの構成要素は自分にとっては外界だと思い込んでいる、あらゆる存在が多分に編み込まれたものなのかもしれない、というか。反対に外側だと思っていたものにも、自が介在していたり。
窓を設定するような一方的な距離感では測定不能な、関係とはもっと複雑怪奇なものだと感じたのかもしれなくて。
変遷を一個ずつ踏んでいくと長くなってしまうので、自分の作品の中で、重要な変遷の一つをあげるとするなら、恐らく、この自と他という構造に纏わる事柄についてなのだと思います。
近作まで話を飛ばしていくと、たぶん、アーティストたちはみんなそうなのかな、とも思うんですけど、この2~3年のことは制作に影響を与えていると思います。
―やはりコロナ禍でしょうか
そうですね。ウクライナのこと、経済不安のことなどいろいろありますけど。フェイクニュースなどもそうですね。タモさんがこの間、新しい戦前と表現していましたけど。
元々溜まっていたものが噴出している、というような印象もあるんですけど。
―その噴出したものというのは長嶺さんからみると今までの歪みなのでしょうか、矛盾からくるものなのでしょうか?
難しい質問ですね。一旦別の軸から考えてみようと思うのですが、ぼくが生まれたのが1988年なんですね。バブルが終わる辺りで。ソ連崩壊の直前とも言える年だと思います。
近代という場所から時間が続き、今僕たちが生活している現在という場所に辿り着くわけですけれど、それについて僕はリアリティをあまり持てていなかったんですよね。
きちんと研究している人達だったら感じ方が違うのかもしれないんですけど、僕は自分が子供の頃を過ごした90年代や00年代、それから現在に至るまで、それ以前の物語といいますか、歴史が続いている様に感じられていなくて。断絶しているというか、宙に浮いているような感覚になっていたんです。
でもこの2~3年の衝撃は、近代と現在が地続きなものとして、無知な自分に対しても肌感覚として貫いてきたというか。今まで過ごしてきた世界と別の世界に来た様にも思う、といいますか。
―一気に実感として捉えられるようになった、という感じですかね
それともこの2~3年の間にだんだん実感してきた?
自分が絵画というメディアを扱っているということもこの実感に影響を与えているのかもしれないと思っていて、絵画はそれまでの文脈が前提にあるというか、積層があることだ、と思っています。その積層を無視して描くという事は難しく、また無視せずに絵を描くというのもまた難易度の高い事で、どこか「絵を描いている」という状況をずっとふわふわと抱えて来てしまったのかもしれないのですけど、その意識が変わってきたのだと思います。ちゃんと抱えていかなければいけないのかな、というか。歴史、時間が流れている中に今の自分達がいて、絵を描いているのだ、ということを。そういった自覚の推移が、この数年の出来事と連動しながら、じわじわと実感に結びついた様に思います。
なんというか、絵を描いていたって基本的にはなにも直接的には救う事が出来ないわけで。この現状の中で絵を描くという事は、必然的に、答えがでるはずのない事にぶつかり続けます。現在の制作は、そうですね…、立っている場所の見つめ方を変えるといいますか。あらためて考える、ということをはじめているのだと思います。

僕は絵画がすごく好きです。なんなんでしょう、空間がポコッと生まれるというか、この世になかった空間が急に生成できる、というか。すごい事だと思います。それって写真なんかも似た機能を持ってますし、映像や映画なんか動画でそういう事が出来て、鏡なんてこの世をもう一つ作れるし。今はVRとかもありますよね。
絵画もそういった、空間を生み出すというポテンシャルを持っているものだと思うのですが、例えば写真だと「過去」を扱うというか、かつてあったものを扱う、というか。簡単に写真を一言で括る事は僕には出来ませんけど。
映画やVR空間はスクリーンの向こうやその空間の生成強度が高くて、シートに座っている事を忘れる事だってあるぐらい。でも、空間を強力に生成出来るから、平面で静止画のメディアより強力なのかといえば、勿論そうではなくて、それぞれのメディアには得手不得手というものがあるのかなと思います。
例えば絵画も、美術館などで鑑賞される作品はどんな作品であろうと、特殊な事がない限りは、全て「かつて描かれたもの」なのですが、その「かつて」のニュアンスには絵画の独自性があると思っています。
そうですね、例えばボナールの浴室のシリーズというのがあるのですが、あの人ってのちに妻になるマルトって人がお風呂に入っている姿をよく描くんですけれど、もともとボナールってモデルにポーズを取らせるみたいな事はしなかったらしいんですよね。一瞬目に留めたその記憶の中から描き始めるらしいのです。晩年になっても浴室シリーズを描き続けるのですが、いちばん最後の浴室はマルトが亡くなる直前から亡くなった後にかけて制作しているらしいんですけど、その絵は、すごい事が起きている絵だな、と思っていて。
絵画は「不在を媒介する」というか、絵画ってここにないことと契約を結ぶことによってつくられる、というか。そんなポテンシャルがあると思ってしまう一つの例だと思っています。
また、「不在の契約の仕方」にはいろいろある気がして。すごく気になっている作品があるのですが、多分あらゆる作家が気になっている作品ですが、ベラスケスの「ラス・メニーナス」という絵があります。王と王妃を描くベラスケス自身も描かれているという不思議な絵なんですが、なぜ画面に描かれたベラスケスが王と王妃を描いているとわかるかというと、室内の奥に小さな鏡に映っているからなんですね。つまり、ここに描かれているモノというのは、おそらく王か王妃が見ている風景なんです。
この「ラス・メニーナス」は鑑賞者の存在がセットで描かれているというか。絵画の中に発生する空間と、絵画と鑑賞者の間に発生する空間がおかしいというか。その原因はもしかしたら発注主の不在により、想定されていた鑑賞者と絵画の関係が捻れた事にもあるのかもしれませんし、わからない事だらけな絵なのですが。
話が少し変わりますが、存在というものに対しての見方や感じ方が気になっていて。
端的にいえばインターネット、スマートフォン、SNS以後の存在の仕方がそれまでと変わったのかもしれない、というか。目の前の人が、その目の前の状態だけで存在しない、というか。
当然のようにいろいろな人間たちが別々の場所で別々の時間に何かをして過ごしている、或いは、過ごしていたということを、僕らは手のひらで知っています。
例えばですが、今日はホルベインの担当者の方とはじめて現実でお会いしましたが、以前からメールでやり取りをさせて頂いていて、その事が、今直接お会いしている状態に対しても何かしらの影響は与えているんだと思います。さらにSNSも知っていて、インスタグラムで普段着の写真なんかも、もしも見ていたら、お会いした時の感じ方は結構違うと思うんですよ。ゴーストを纏う、というか。
今あげた例は些細な事で、何も真新しい事ではなく当然の事を言っているとも思うのですが、これが広範に常に起こり続けているとすれば、存在の仕方、認識の仕方が加速をつけて変わり続けるという事はあり得るのではないかと思います。それは絵画の鑑賞体験にも、複製技術とはまた違った影響を与えるのかもしれません。
そういう印象をこの世界の存在に対して持っている、ということを、絵画の中に持ち込むというか、今までと違う存在の仕方、認識の仕方があるとするならば、何か新しい関係が描ける気がしていて。
現段階ではそれはなかなか実現出来ていないと思っているのですが、例えば、ムーブマンが作る事のできる絵画空間の中の関係が、鑑賞者との関係を考える上でもすごく重要に感じていたり。そういったものを足掛かりにして試していく、ということをしていると思います。

キャンバス・油彩 1940×3240㎜ 2022年
最近描いている絵で、例えば今そこの後ろにある絵なんですけれど、これは僕の職場がモチーフになっています。大学の助手をやっているのですが、助手室という場所で主に仕事をしていて、そこで一緒に勤めている僕を含めた4人を描いています。
「助手展(展示タイトル:P-201)」という大学内のギャラリーを使った展覧会がありまして、それに出すために描いていたのですが。
―この作品をみて思ったのですが、「妙にリアルな臨場感」があるんですよ
正に助手室の風景を窓からみているような印象をすごく受けました
実際すごく散らかっています(笑)。
そのような感想はとても興味があります。
鑑賞者の存在や、他の同僚(作家)の作品も同じ空間に展示されるという事をすごく意識して描いているというか。
学生や教授など、顔を見知った関係の人達が鑑賞に来るという事だったり、ここに描かれている人物が同じ展示空間に置かれた作品達の作者であるという事だったり、実際にモチーフになっている助手室が展示室の上の階にある事だったり。
それらが取っ払われた状況下でどうみえるのだろう、というのは興味がありますね。
昨年の個展では、そのギャラリーの人間関係をモチーフにしたり、アトリエメンバーを画面に登場させて、みんなで画布を張る様子をモチーフにしたりしていました。
今はこういった、絵画を描く事自体や、描く為に必要な生活や労働の周辺事項の様なもの、自分にとっての第一次ソースというんでしょうか。そういったものと関わりながら何か捕まえようとしている、という感じです。
―鑑賞者に意図的に特定の印象を持たせようとか、そういった意識はありますか?
あると思います。イタズラに近い様なこともありますし、逆に極端な印象を持たせないようにしようとする場合も、あるとは思います。
「ゴールデンレコード」ってご存じですか?ボイジャー1号と2号に搭載されている、人類が生きていた証拠みたいな。50か国語くらいの挨拶が録音されていたりするんですが。宇宙人がいつかそのレコードを発見することを想定して、色んな仕掛けがしてあるんです。僕は絵画にもそれに近い印象がある気がします。
この作品は学生や教授などの狭い範囲の見知った人が見る事を想定して描いたと先ほど言いましたが、それは「異星人に向けて描く」とは、一見全く逆のベクトルだと思われると思うんです。
でも絵画って、先ほども言いました通り、いろいろな蓄層を持っています。その分まっさらに新しいものを描くというのは難しいというか、白いキャンバスが実は白くないんですよね。制作者も意図していないコードが延々と発生するんだと思います。まあ何だってそうかもしれませんけど。これだけたくさんのものが溢れた世界の中で何かを選んだり行ったりする事は、無意識でも態度ですから。
発生するコードは作者の想定よりも遥かに膨大で、例えば引用だとかの一言で済まされるレベルではないと思っています。たぶんそのコードは絵画が完成した後にも増え続けるのかもしれません。だから仮にすごく狭い範囲の、例えば僕の職場の同僚の顔を描いたとしても、それがそのまま職場の同僚の顔のままでい続けるかというのは、予想の出来ない事かもしれないと思うんですよね。
作者がコードを剪定していく様な事にはあんまり興味が持てないですが、能天気な筆が自由という訳でもないというか。絵画はそこに何が描かれようが、その絵画自身だけで完結する事はないと思っていて、常に環境と、鑑賞者のいる世界達と掛け算されるんだと思います。絵画を選んだという選択も含めて、選ばせられ続けているんだと思います。
絵画を鑑賞する体験というのは、ボルヘスの小説に出てくる、砂の本のページをめくる様に魅惑的な事だと思います。
ただし、積極的な鑑賞者に出会えなければ、背表紙の模様を眺められるだけの、閉じたままの本になってしまうのかもしれません。
―鑑賞者が絵画を鑑賞することで作品と一体となる、セットになるということは、写真との対比として、絵画とはそういうものなのかな、と思います
写真はあくまでも過去の切り取りであって、逆に絵画はまさに描いたその時の雰囲気が残っているし、作者が手を付けた状態がそのまま残る、創作されたものですよね。
作者の意思を感じられる、というか。そこが写真と絵画の違うところではないでしょうか
絵画の写真との違いは、恐らくたくさんあると思いますが、立体物である絵具を使っていることは、かなり重要で明確な差だと思います。先ほどの映画などとの比較の場合についてもそうだと思います。
イメージ、イリュージョン、絵画には張られた布の向こうに空間を虚偽する能力がある訳ですが。
実際には塗られているとか、平面であるとか、布のこちら側に絵の具がモノとして存在する事、色として存在する事、制作者の引いた筆致が残る事。現実の理側の空間での出来事達と、鑑賞者がこちら側にいるということにもつながりを感じています。例えば虚偽された空間と、理の空間の境目に置かれた絵の具とは、どちらの空間に属するものなのか、というか。
絵画において「うまい」という表現が用いられる事があります。例えば「筆が決まっている」とか。与えられた行為や物質などの理側の属性と、イメージ、イリュージョン、何かの様に見えるなど虚偽空間の属性、つまり「こちらとあちら」が同居しながら矛盾できるという事が絵画のポテンシャルのひとつとしてあり、その両立矛盾の場所、「宙吊り」の空間への到達を「うまさ」と表現する場合があるのではないかと、現段階では一つ、仮定しています。
―なるほど
長嶺さんのおっしゃっていることにはとても共感できます
長嶺さんとホルベイン

―話はガラッと変わりますが、今回、長嶺さんをホルベイン・スカラシップ奨学生に認定させていただきました
それ以前はホルベインの絵具や画材は使っていましたか?
ヘビーユーザーだと思います。
油絵具と出会ってからは10年以上経過しているのでいろいろ使ってはいて、最初は他社のものを使っていたのですが、いつの間にかこうなってしまった、というか。
今はホルベインを軸に、色によってほかのメーカーのものも、という使い方をしていますね。
―では、ホルベイン・スカラシップ認定前と後でかわった、ということはありますか?
ヴェルネは初めて使いましたが、「ヤバい絵具」ですよね。
―ヤバいとは、褒め言葉ということでよろしいですか?(笑)
透明色というとやっぱりちょっと濁るというか、少し落ちていく印象があるのですが、ヴェルネは色を保持してくれる印象があります。伸びもすごくいいですし。
透明色がすごいと思いました。
僕は一枚の絵画を描いていく中で、いろいろな絵具、色を使っていくのですが、その結果ロートーンに沈んでいく傾向にあったのですが、ヴェルネだけの影響ではないと思いますけれど、ちょっとトーンが上がった、というか。コントロールが効く印象です。
―ヴェルネはかなり違いを感じますか
コバルトバイオレットなんかは全然違いますよね。
コバルトは弱い印象があったのですが、ヴェルネのコバルトグリーンなんかもすごいですね。
レギュラータイプ、HOCのグリーンシリーズと比較するとヴェルネのコバルトグリーンは隠ぺい力が全然違います。
―ヴェルネは油絵を描かれているほかの奨学生たちでも、高価なのであまり使えなかったという方がかなりいらっしゃったのですが、奨学制度を利用して思う存分使うことができるようになって、あらためてその価値に気付かれた方は多いですね
薬物を与えられた様ですね(笑)。これは今後も買っちゃうかな、と思います。
―ヴェルネだけで描いてみようとか思われたりしますか?
いや、そういうことにはならないですね。HOCのAシリーズやBシリーズでも、なんというのでしょう、幅の作り方だと思うんですよ。
先日提出したホルベイン・スカラシップの課題で提出させて頂いたレポートにも書きましたが、マースオレンジなどもすごく気に入っていて。乾くと引いてマットになるんですが、ああいう絵具もあるから光沢のある高級な絵具も一つの幅として見えてくるというか。逆にAやBシリーズの絵具じゃなきゃ出来ない事もあると思います。高級な絵具だから無条件にいい訳でもないと思います。
―今回、ホルベイン・スカラシップへの応募は初めてだったのですか
また、ホルベイン・スカラシップのことはどのようにして知られたのですか
初めての応募でした。
第33回ホルベイン・スカラシップ奨学生の菊池(遼)くんが同じ大学で。彼がスカラシップ奨学生になって、インタビューを受けていて、展示もやっていて。これはおトクなんじゃないかと思って(笑)。
―長嶺さんの思った通りになったという訳ですね(笑)
非常に助かっております(笑)。
―長嶺さんは近々、展示の予定はありますか
…ないですね。
展覧会を出来る機会を探しているところですね。
―第33回のホルベイン・スカラシップ奨学生の皆さんには「成果展」を我々の方で企画し開催、34回のみなさんも来る5月に開催予定となっています
長嶺さんの第35回奨学生のみなさんにも何かしらご紹介できたら、と思っています
ぜひお願いしたいです。展覧会の機会を増やしていけたらと思っています。
―お話をうかがえばうかがうほど、その真面目な人柄や、あらゆる事象に真剣に向き合う姿勢が感じられる長嶺さん。
今回はアートに纏わることに限定された形になりましたが、ほかの話題についてもぜひお話を聞いてみたい、と思いました。
制作にもとても真剣に取り組む長嶺さんを私たちは製品を通じてできる限りサポートしてまいります。

プロフィール
長嶺 高文
NAGAMINE Takafumi
個展
グループ展
その他
HP http://www.nagaminetakafumi.jp/